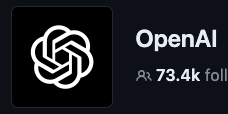「不道徳的倫理学講義」について

先日星野さんに教えていただいたので、早速読んでみた次第でした。備忘録がてら。適宜解釈してますのであらすじというわけでもないです。
「不道徳的倫理学講義: 人生にとって運とは何か (ちくま新書)」
本書では、人生はしばしば賭けや運の側面を伴うことを念頭に、道徳や倫理に関する理解の歴史を捉える(14)。そして、賭けや運の要素を取り込んだ倫理学、つまり不道徳的倫理学を提示しようとする。賭けや運は偶然や必然と結びつき、運命や宿命、さらには自由とも関連し、哲学の根幹的な問題と結びついている。
この世界の出来事や自身の人生が全て賭けや運であるという場合、道徳や倫理はほとんど意味をなさない。道徳や倫理が語られるためには、賭けや運ではない側面や、あるいはそもそもの賭けや運自体を規定する何かが必要とされていなくてはならない。その一方で、逆にこの世界が既に決まったものとしてあり、全てが運命としてあるのならば、やはり同様に道徳や倫理は積極的な意味を持てない。道徳や倫理は、人々が自由に何かを決められるという場合、その決定の指針として必要になる。
序盤で語られるオイディプス王の逸話は、賭けや運を考える上で重要な出発点を提示している。すなわち、彼の一つ一つの自由で偶然的な意思決定は、しかしながら、既に予言され定められた運命としてあったことが最後にわかる。さらに、当の運命に抗おうとするがゆえに、あるいは抗おうとしたゆえに、結果的に予言が実現される。予言の自己成就までを含み込んだその逸話は、賭けや運が究極的には運命の中にあることが示される。せめて可能なことは、オイディプス王が最後に行ったように、自らの目を潰すことしかない。それは運命に従うことを受け入れる象徴でもあるが、目を潰すことだけは自分の意志で行えるのだという強い自由の主張でもある。
道徳や倫理の歴史は、賭けや運、逆に運命に人生の全てを委ねるのではなく、人生における選択を徐々に人間の側に取り戻そうとする過程として考えることができる。例えば、プラトンによる『ゴルギアス』では、ソクラテスが死後の世界を紹介しながら、生前の賭けや運の良し悪しは死後の世界において判定され、次の人生に影響を与えることを主張する。生前の行き方の良し悪しが次の人生を規定する以上、人々はよく生きようとしなければならず、よくあろうとすることが重要な意味を持つことになる。さらに、死後の世界において次の人生を選択するのは、その選択の順番自体はくじ引きによって決められるとはいえ、自分自身であるとされる。道徳や倫理と自由の範囲が広がり始める。
だが、よく生きようとすること、よくあろうとすること自体、究極的には賭けや運から逃れられるわけではない。生まれや環境によって、徳を身につけやすい人もいればそうではない人もいる。さらに、どんなに徳を身につけても、賭けや運に恵まれず、不幸なままだという人もいる。来世思想は少しはこの世の不幸を軽減するかもしれないが、こうした思想そのものが、時代の中で廃れていくこともある。徳そのものが幸福であるとみなすことや、徳とはそうした外部からの不幸に動じない超人性の獲得であるとみなすこともできる。しかしながら、これらもまた、今日的にはもちろん、当時にあっても容易には実現できない賢者の教えだった。
道徳や倫理の発展は、人間の内面としての意図と、その行為の結果を分離させつつ、さらにその両者の関係を捉えるようになる。アダム・スミスの『道徳感情論』では、意図こそが道徳や倫理の対象として捉えられ、その行為の結果は偶然や運の要素が入り込むために議論できないことが主張される。同時に、その一方で当の意図の道徳性や倫理性は、行為の結果によっても影響されてしまうとして、相互の不可分性についても言及する。神の見えざる手が示すように、個々人の意図とは別に、その集合は別の社会的成果を生み出すことにもなる。それはおそらく現代の運命論の一つの形であり、まさに見えざる「神」を想起させる。
「運は徳を挫く。この世界は運に翻弄されるがゆえに、人はそこから離れて内面の世界に安住の地を求めることもあれば、この世界とは別の世界(彼岸)に確実な幸福を求めることもある。しかし、どこまでも道徳の敵として立ち現れるかに見える運とは、本当に忌むべき厄介者にすぎないのだろうか(278-279)。」現代に時代を移しても、問題の焦点が変わるわけではない。むしろ、内面の世界にすら、運は入り込んで影響を与えている。
バーナード・ウィリアムズは、道徳的運を議論する中で、ゴーギャンの例を提示する。彼はある時、画家として、妻や家族を捨ててタヒチに住むことを決意する。それは道徳的には非難されるべきだが、結果として、彼の画家としての大成には繋がったのだから評価されるというわけである。この時、ゴーギャンは二つの道徳を生きていることになる。一つは家族はかくあるべしといった狭義の道徳であり、もう一方は、自身はどう生きるのかといった広義の道徳である。本書では、後者の道徳を倫理と呼ぶ。ここにいたり、道徳と倫理は異なるものとして分けられ、さらには、道徳と倫理の間を架橋する可能性こそが、賭けや運であるという視点が見出される。
もちろん、こうした賭けや運の良し悪しは、その成果に依存する。道徳と倫理が、明確な出発点と着地点として用意されているわけではない。しかも、うまくいっても、うまくいかなくても、いつまでもその人は道徳と倫理に悩み続けるかもしれない。こうした賭けや運は、自らが引き受けて自覚的に行うものばかりではない。われわれの日常は、むしろ無意識の賭けや運のつながりであり、例えば自動車事故のように、突然の不幸に見舞われることも常にありうる。誰であっても、人は賭けや運に悩む。この時、道徳や倫理の内側はもちろん、両者の架橋を巡ろうとすることが、結局のところ個人の形を形成することになる。
運
運についてはいろいろ考えるところもあり、昔読んだ「ツキの法則―「賭け方」と「勝敗」の科学 (PHP新書)」の印象が強いわけですが、倫理や道徳との兼ね合いとして考えるのはおもしろいなと思った次第でした。運とか直感とか、何かつなげないか考えている最中でした。